雨の日はビチョビチョじゃないの?w
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4418121390/
それでも日本初の水虫患者は幕末なんだし草履のほうが清潔だったんだろ
なんて文句のつけようのない>>2
こんなの履いてたんでしょ?

http://www.officiallyjd.com/wp-content/uploads/2012/03/20120313_oguri_26.jpg
合戦とかする時にこんな草履とか履いてたら戦えないとか思わなかったのかなw
>>4
柔らかくて軽いから不整地な場所でも動きやすい
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1391066180/
良い意味で土と一緒に生きてて近かったんだろう
俺は泥臭い方が好きだ
言ってみれば、普段サンダルみたいなのを履いてる状態だよね
運動したり戦ったりていうような用途には全然向かないよねw
草履でコンクリ歩くと痛いけど
土だと歩きやすいんだぞ
貴族は木靴を履いていたと忍たま乱太郎でいってた
俺山歩きするからわかるけど
ワラ草履みたいなので舗装もされてない道を歩くってどんな罰ゲームだよって思うもんw
木靴っておしゃれに目覚めた厨房かよ
日本の気候だと蒸れるから
日本家屋なんかも日本の風土にあった作りをしてる
>>16
今はみんなちゃんとした靴を履いてるじゃんw
湿度が高すぎるから
マジで雨降ったらどうしてたんだろう
即効水を吸ってべちょべちょになるよね?w
>>18
靴だってべちょべちょになるだろ
革がとれる生き物を畜産してなかったから
日本のサムライとか忍者とか
あるいは鎧姿の武者の画像が海外で紹介されるたびに
足元がワラ草履なのを見て恥ずかしい気分になるだろw
日本の気候だとブーツやスニーカーに靴下だと不潔だしな
草履とかサンダルのほうが通気性はよさげ
サムライの格好とかも足元まではカッコいいなとか思うけど
足元を見たらワラ草履だからずっこけるだろ
うわー、恥ずかしい文化だなって思うよなw
いつでも砂浜で遊べるじゃん 島国だし
まぁ温厚な民族だったんだろうなというのが
ワラ草履から推測できるよな
しょっちゅう戦ったり喧嘩してるようなら
サンダルみたいな足元だと喧嘩もまともにできないわけだからw
>>36
サンダルと温厚さは全く関係がない
それならスパルタ人はどうなる
肉を喰う文化が発達してないので革製品の文化が発展しにくい生活
あとは高温湿潤の環境のせいでビジネスマンでもたまにスリッポン履いてるオッサンがいるが残念でならない

http://www.chiyodagrp.co.jp/special/rekisi_dokuhon/img/120927/02.jpg
ジャアアアアアアアップwww
>>40
うわー
足元だっさ
いつ見ても靴を何とかするっていう発想にならなかったのかなと思うわw
西部劇とか見たらブーツ履いててカッコいいだろ
一方そのころ日本ではワラで編んだ草履だったんだろwあちゃーw
中国でもう既に靴の文化があったんだから
知らなかった訳はない
日本の環境に向いてなかっただけの話
実際舗装された道路じゃなきゃ草鞋の方がいい
江戸時代は今より寒冷な気候だったんだろ?
夏はいいとして冬はやっぱり寒そうだよな
>>53
足袋履いてれば別に問題ないでしょ
ハイヒールとか道端に糞が捨てられまくってるから開発されたんだったな
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/441811405X/
高い下駄履いた天狗みたいな衣装はカッコいいと思うけどね
雨の日意外実用性ないけど
え?え?
お前らなんで擁護しちゃってるの
どう考えてもダサいし機能性も低いだろw
>>58
ブーツが機能性に優れてるってのははじめて聞いた
土の上歩くには草鞋の方がずっと機能的だよ

http://www.gamecity.ne.jp/dol/gallery/image2/idd01.jpg
ヨーロッパ人なんて大航海時代ですらこれ
かっけぇw
一方、日本はこんなのをつい最近まで履いてましたw

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1b/b2/19c9c0f05e3fd8eeed2152c522058f40.jpg
日本は稲を主に食べていたのでその余ったワラで草履を作って履いていた
ヨーロッパでは肉を主に食べていたのでその余った皮で靴を作って履いていた
ただそれだけの違い
>>79
革はあんまり実用的じゃないから実用的な木靴や貴族は布靴(底は革)がわりと強かったけどね
平安にはサンダル型以外の履き物として、沓(木に漆を塗ったもの。スリッポン型。貴族の常用)、靴(皮のブーツ。乗馬用。北方騎馬民族由来)、糸カイ(絹糸を編んだズック靴。貴族男児用)、麻カイ(麻布のズック靴。下級武人用)、草カイ(藁ブーツ。警察用)
なんかがあるよ
そりゃヨーロッパ人がやってきたときに
チョンマゲにワラで編んだ草履を履いてたら
未開の地の民族と思われても仕方ないわw
江戸時代のエコ社会だから草履は再利用できる点で優れてるし日本の風土にもあってる

wp-content/uploads/imgs/bLXy5HS.jpg
>>85
あかん後半なに書いてるかわからん
>>259
多分、彼らはその土地土地で洗練された文化の中に生きており、野生(つまり風土の中に生きる)であると言える。
真に野蛮と言えるのは、これらの制度から逸脱し、粗暴を働くものであるってことじゃね?
だから自分たちの価値観だけで野生(野蛮)を判断するのではなく、よくよく相手を理解した上で判断しなければ本質は見えないよってことだろな。
>>273
なるほどありがとう
いい事言ってんな
革なんて加工がめんどいうえにそんなに手に入るものでも無し
ボロになっても我慢して使い続けないといけない
しかも水虫になるしくっさい
一方草でできた草鞋は材料が豊富なため使い捨てできまくり
植生が豊かでアホほど草が生える日本だからこそできること(道路の草刈りめんどいけど)
女で初めて富士山の頂上まで登るってイギリス人だったかが言い出した
↓
当時の幕府困って多くの付き添いと一緒に行くことを渋々了承
↓
わらじが何足もいるだろうと思い用意してやる
↓
イギリス人はちゃんと革靴履いてるからそんなの全くいらなくて全部捨てることになる
この話を聞いて爆笑したわw
わらじなんて履くわけないじゃんw
ちなみに、ちゃんとした靴を履いていたイギリス人たちは全員登頂に成功
一方、わらじの日本人たちは二十数名全員が脱落撤収というみっともなさw
マジでw
日本に豚がいてくれればなぁ
>>103
日本では弥生時代中期頃から東南アジア原産のニシアジアブタの養豚が始まってるよ。
長崎卓袱料理が成立した1700年代初頭には薩摩藩などが養豚を行って大阪や江戸でも豚肉を販売してる。
>>134
へー
食生活変えるほど豚食が大規模に伝播しなかったのは仏教のせいなのか 、寒くて豚に食わすものが無かったのか、
惜しいなぁ
>>143
浄土真宗などは最初から四足動物の狩猟や肉食を認めていたし、
室町時代には浄土真宗本願寺派のトップが四足動物の狩猟や肉食を推奨までしている。
戦国時代の陣中日記の中には農民が鹿肉に味噌を塗って焼いて食べてるのを見た雑兵らが俺達にも肉を食わせろと騒いで行軍が止まったことを嘆く一節もある。
近年の動物考古学による発掘調査では戦国時代中期から江戸時代初期にかけて使われていた庶民の共同ゴミ捨て場からは調理痕がある犬や鹿や猪などの骨が多数出土してるし、長崎で成立した豚の角煮などの卓袱料理は大阪や江戸でも流行している。
福岡藩の藩誌には朝鮮通信使に豚肉料理を出したら「こんなに美味しい豚肉料理は朝鮮にはない。毎日食べさせて欲しい。」と言って他藩に献上する予定だった献上品を差し出して来たという主旨の記載もある。
鹿や猪などの野生動物がたくさんいたから養豚の必要性が低かったって感じじゃないかな?
そもそも仏教の教えを守って肉食を行わなかったってのは戦後に江戸時代は暗黒の時代との印象を植え付けるために作られた話だしね。
農業国の定めで日本では餓死者が出るような飢饉が何度も起きているのに、
山にいる鹿や猪を獲らずに両親や子供や妻を餓死させるってこと自体が仏教の教えに反していませんか?ってことなんだけどね。
>>214
肉食は薬食いと言って、忌避はされていたけどまったく食べていなかったというわけではない
そもそも高価だし庶民はあまり食べてないと思う
あと家畜の牛や馬は農業の補助してたから、食べたら人手がかかりすぎるから食べるのは最後の手段だわな
こいつ見た目のことしか言わねー
日本の気候とか材料の問題とかのレスには完全スルー
道が舗装されてない時代って想像したら凄いよな
足元なんてすぐに汚れて泥だらけだったと思うぞw
だから町民の足は下駄と雪駄だって言ってるだろww
武士とかが動きやすい草履にしたんだろ
>>120
武士というより長距離の移動時に草鞋を履いた
下駄とかだと長時間は歩けないから
旅の前に何足も買って履きつぶすのが普通
足袋なんて靴下と変わらんだろ。単なる布なんだから
大工とかが履いてる地下足袋と混同してないか?しかも地下足袋はゴム製品なわけで
>>128
江戸時代初期くらいまで皮足袋(鹿皮をなめして燻し耐久性を高くしたもの)が普通
後に主流になった布も今の白足袋と違って麻布を紺などに染めたものが多かったよ

http://www.nara-u.ac.jp/hist/_userdata/d1-2b.jpg
↑
マジでこんなのだったんだろ
うわーwどこの未開土人だよ
そりゃ富士山に登れるわけないわw
日本のファッションは垢抜けんのーw
環境によって育つ文化が違ったというだけなのに何を言ってんのこの人
日本人や日本の文化って昔から劣ってたんだなと恥ずかしいよな
椅子の文化もなかったんだろ
地べたに座る文化w
日本は発酵の国じゃし、カビやすいのは扱い難しくなるだろうね
出島辺りで革の加工技術とか広まらなかったのかな
>>154
広まったところで供給源が少ないから……
粘土質の土壌が多く最も降水量が少ない地域でも年間90日間は雨か雪が降ってるのが日本の国土なんだよね。
だから木靴のようなタイプだと湿気が抜けずに腐りやすいし、革細工はえたが独占する神事・軍事技術だから武家か神職しか使えなかった。
そもそも欧米の靴が今の形になったのは19世紀末のイギリスだぞ
昔の欧米人の男ってパンプスやヒールつきの靴を履いてたし修道士はサンダルを履いてたんだぜw
靴を履くのはゲルマン人の文化が由来で、イタリア人やギリシャ人はサンダルだったよ。
世界中どこを見ても、温暖湿潤で夏がきつい所はサンダルの文化が発達してきた。
エジプトしかりイタリアしかりギリシャしかりな
みーんな今みたいな革靴を履き出したのはイギリスのスーツが広まってからだわ
だから靴を履く=文明的、ってのはちょっとズレてるな。
>>161
確認可能な中で最古の革の靴はデンマークの泥炭地で発見された紀元前数百年くらいのゲルマン人男性遺体が履いてたものと思う
四角い皮の中心に足置いて足首からゲートルで固定した簡素な履き物で、靴ってイメージとは遠いけど
だいたい十六世紀まで皮革加工技術が未熟で革が臭いから香水に浸してたのに、お貴族様がそんなもの履かんわな
十七世紀中盤にようやく貴族にファッションとして革ブーツが好んで履かれるようになったんだよその後にすぐ絹のハイヒールに取って変わられたけど
正直、靴は機能的じゃないし合理的じゃない
未来には完全に道路とかが屋内環境に成って、あってもスリッパ程度だろ
靴は足にダメージを与えすぎ
そこらじゅうで稲作してたんだから、草鞋ならどんどん新品使っても惜しくないじゃん
足袋を履かなくてもいいし経済的だろ
当時の人たちは現代人より足裏が丈夫だったから、俺らには分からんだけのこと
いや、わらじなんてマジでダサいし機能的でもないだろ
どうして足元だけ日本人はおろそかにしてたのか不思議でしょうがないw
>>182
機能的じゃない、とは言えないかな。
侍や木こりや狩人みたいな足を保護する必要がある人は革の足袋を履いていたよ
それで足の保護は充分だった
公家は大陸伝来の沓を履いていたが、ついぞ民間には広まらなかった。
革そのものがあまり流通していなかったし、湿度の問題があったんだろうね。
草履はセンスないと思うけど
天狗の高下駄みたいのはかっこいいと思う
>>184
ヨーロッパ人が新天地を求めたり、探求心から外の世界に出ていったのも
やっぱりしっかりした靴という文化が背景にあったからだと思う
日本人が一か所に留まって内向きな文化しか発展させることができなかったのは
草履や下駄みたいな足元文化だから、自然と行動力がスポイルされてたんだと思う
もし仮に今の時代もワラ草履が日本の足元文化なら
例えば登山とかジョギングなんていう文化は発達してないと思うよw
ていうか、登山なんかもヨーロッパ人が日本にもたらしたものなんだけど
彼らはしっかりとした靴を持っている文化だったから、山の自然の中にレクリエーションとして入り込むということができたんだろうけど
日本人はワラ草履だからそもそもヨーロッパ人に教えらえれるまで
そんな発想も文化もなかったんだろうね
実際ワラ草履なんかで登山を楽しむなんて無理だし
ほんと恥ずかしい
足元がワラ草履だったというのは、日本人の行動力に大きな影響を与えてきたと思うよw
>>205
だから、日本にも富士詣りを
始めとする、山登りの文化が
ちゃんとあったんだっての!
>>205
登山やら海水浴は産業革命以降の中産階級のレジャー文化の中で生まれた趣味な
日本では山に入るといっても巡礼の一種(レジャー化してたけど)だから登山自体を楽しむという発想がなかった
ちなみに草履や高下駄がガンガン山登るけどな昔の人は。山から降りたら宿で飯盛り女呼んでお楽しみ
>>205
それはない
ヨーロッパ人が新天地を求めたのは土地が痩せてたのと、宗教問題さ。
人口が増えすぎたせいで大航海時代のヨーロッパの下級民の暮らしはそれはひどいものだった
だから新天地への進出と貿易で生きる糧を得ようとしたのさ
下駄も革靴も痛いんだよ
なんであんなに履物って痛いんだよ……
わらじと下駄って不思議な履物だよな。
防御力も低そうだし寒さにも弱い。
ただ家庭内手工業下で生産が可能だったからだろうね。あと軽さとか?
>>191
下駄はともかく、草鞋は使い捨てるのには最適だったんじゃなかろうか?
戦ですぐ足怪我しそうだよな草鞋
まあ仕方ない。山だらけで革製品もあまり取れない国だったんだもの
>>202
革足袋や毛履使ってるから大丈夫だろ
考えてみると、外の世界に進出していった国って
ちゃんとした靴を持つ国ばっかりじゃね?
これって新しい学説になるかもw
しっかりした靴があるからこそ行動力も行動範囲も広がるわけだし
ワラ草履を履いてる民族が、海の向こうがどうなってるのか調べに行こうなんて思わないもんなw
俺だってワラ草履を履いてたら、郵便ポストにハガキを投函しに行くだけでも億劫だわw
>>220
だから下駄があるって言ってるだろ
下駄と足袋履いてれば普通にOKなんだよ
昔の事に何故そんなにムキになれるのか
は?富士山とかそういうのに登るのは修行みたいな仕事の奴だろ
登山みたいなのは娯楽としては庶民に全くなかった文化だよw
その理由が足元が草履だからなんだよw
>>225
伊勢参りとか諸国行脚は庶民の観光だろう
昔の人は仁ママくらい足の裏強いはずだから不思議はない
お前らなんで擁護してるんだよ
何度も言うけど、ワラ草履なんてダサいしみっともないし
消し去りたい過去だろ
俺いっつも思ってたよ
武将とかサムライとかの格好してるイベントで外国人観光客もたくさん集まるんだけど
足元がワラ草履なのを見て超恥ずかしいって思ってたよ
お前らもそう思うだろ
なんで足元に藁で編んだサンダルを履いてるのかと
あの部分だけでファッションとしてガッカリだろw
>>235
ちと思想が偏ってるのではないかな
ダサい、カッコいい、そんなことは重要じゃない。
なぜその国や地域ではそういう文化が発達したのか、
それに付随して人々がどんな工夫を凝らして、どんな文化が生まれたのか。
それが文化的かってことじゃない?
みんな違ってみんないいのさ
日本でなぜ生まれなかったのか不思議なのが
靴と椅子の文化って言われてるよねw
どっちもかなり恥ずかしいw
>>246
そんな恥晒しの子孫がお主か
これ以上生き恥を晒されるおつもりか
若輩ながら拙者が介錯を承り申す
疾く御腹を召されよ
草履って靴の一種だろ、靴の文化あるじゃん何いってんの
とりあえず、>>1にセンスがないのは確かだな
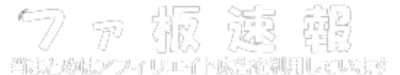


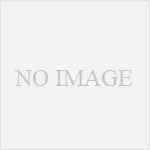
コメント
スレ主がこわい
なんでそんなに草履sageするのか
平安時代にクツはあったし、戦国の世に腰をかけるものだってあったわ。たわけが。
もしや特定日本人か…
顔真っ赤にして日本sageにこじつけて、ハズカシイ奴だな
実際、昔から稲作が盛んだったから、ってのが主な理由じゃないか
材料の藁はいくらでもあるし、水辺での作業ならサンダルのが都合がいいし、履き潰したら燃料にもなるし、実に合理的だ
ネタで立てたスレに顔真っ赤にして「日本sage」とかww落ち着けよ愛国厨・・・w
ネタで立てた(本気でないとは言ってない)
スレ主は草鞋に親でも殺されたのか?
その時代の環境、文化、材料など一切考慮せずに外見だけにこだわるとか、オシャレに興味を持ち始めた中学生かよ
かっこよければ機能性関係ないとか言っちゃうタイプの人間かな?
美意識は時代によって変わる
家に履物を脱いで上がるから脱ぎやすいほうがええじゃろ
1の釣りやろ、ほっとけばいいのに構うからややこしくなる
※7
草鞋に親殺されるってどういうこと?
足袋は一番機能的でカッコいい履物だと思う
みっともない・恥ずかしいと思うのなら、さっさと生まれ変わればいいのに
>※10
草履じゃなくて、下駄で時代劇の江戸っ子みたいに手にはめてぶん殴ったんじゃないか?
草鞋しかなかったんだ、しょーがない事だよ。
的を射た反論はすべてスルーwww
クソムカつく>>1だが知識のあるレスを拾ってきてる事だけはここの管理人を褒める
※5
はいはい笑
日本嫌いなのはわかったから笑
どうせ>>1も「家の中で靴を脱ぐ」んだろ
西洋文化が絶対正義なら和室でも革靴履いて欲しいなw
ミズノから出てる草鞋サンダル履くと目からウロコ
素材はともかく、草鞋は人間工学に基づいたハイテク製品らしい
Fラン学生の題名だけ決めたクソ論文みんなで手伝ってるだけじゃねえか
※20
この>>1のあまりの無教養振りに正直頭が痛くなってたけど、おまいのコメント読んですっきりw
夏はわかるが 確かに冬とか雪国の奴らはどうしてたんだ
雪ん子みたいのみんな履いてたのか
あれ 染みそう
日本は革靴が一般の人に定着するまで相当な時間を要したからなぁ。やっぱり気候的、文化的な面で合わないところがあったんだろう。
革靴なら雨の日も問題ないならロブやグリーンで雨の日出かけろよ
こいつヤバすぎる
※24 それは論点が違う
キモすぎんだろこいつ
ネタかと思ったら顔真っ赤にしてぐちぐち垂れるし
主はチョソでしょ…
オレが>>1ならそんな未開の土人みたいな奴が使ってた言語使うのも恥ずかしくて頭おかしくなっちゃいそうだけどな
>>1が全てのレスを日本語以外で書いてたら評価してやった、中国語とか韓国語、英語とかな
未開とかそのへんは一理あるとしても、恥ずかしいと思ったことはないかな。
逆に、リーマンがくそ暑い夏でもスーツ着てる光景を恥ずかしいと思ったことはある。
1は何人なんですかねぇ
天然クロックス大流行の巻
無教養過ぎる
縄文時代に革の靴はありましたが
いまネットを賑わせてる北大ア/フィサークル騒動の顛末を見るに、この手のレス乞食の正体はまず間違いなくア/フィカスだろうな
全部バレてるよ
※22
そうだよ、あの藁で編んだ長靴履いてたんだよ。
草履もあの長靴も藁を叩いてペタンコにしてから隙間なく編み込むからしみないし、あったかいんだぜ?
雪が深くなったらその長靴の下に
木と藁で作るかんじき履いて雪が靴の中に入らない様にするから全く問題ない。
平安時代にクツみたいのなかった?
でも昔の日本では西洋みたいに糞尿があったわけでもないし、家の中では裸足だし、必要性がなかったんだろうね。
浴衣ひとつとっても灰になるまで使う超エコ生活を送っていたしね。
個人的な考察だが草履や下駄が主流だったのは靴を脱ぐ文化があったからだろう。
脱ぐのが面倒な靴よりこっちの方が好まれたんじゃない?
あと椅子があまり広まらなかったのは相手より頭が高いと失礼って言う忠義の心だろうな。
あと草履がダサいって発想が理解できない。ブーツはいた侍や忍者なんかのほうがよっぽどダサいだろう。
日本は完全無欠の国じゃないってだけだろ。
いいじゃないか靴と椅子の文化がない国だったって。
その分、他国の文化を吸収することに抵抗がないんだから。
草履が万能だとは思わないが、四六時中戦争していたとか思ってんのか?
当時の日常生活で足元に防御力がいる状況ってそんなにないだろ?
ウンコもそんなに落ちてないんだろ?
もちろん革靴が登山に適していると知れば良い革靴を作るよ。
黒船がやってきて蒸気機関車を見せびらかした1年後には黒船と蒸気機関車のコピーを作っているくらいだから。
チクチクしてそうだけどなぁ。
でも、鎧にブーツってありなん?
日本ほど履物に凝ってた国もそうそうないだろ
実用としてのワラジ、履いちゃえば見えないのに足裏おくとこの柄に拘ってる草履、江戸時代あたりにはわざとかかとがはみ出るようにして履きにくいものを涼しい顔で履きこなすのを粋とした下駄
外人さんもビックリのオサレ文化だったろうさ
今の靴の機能性は靴がすごいっていうか靴底の進歩がすごいんだろうな
そのころ大陸(中国)を中心としたアジア諸国では布を足に巻きつけて『靴だ!』と言い張っていたw
こいつ、真性アホなのか引き出そうとする策士なのか
何が言いたいのかわからん
海外では靴脱がないから椅子できただけだろ
同様に文化の違いなだけ
スレ主が外国で暮らせばいいじゃん
外国人として生きろよ
めんどくさい
全ての文化を並べてどれが進んでいるという思想は進化主義だね。
自分の知っている事を優れていて正しいものとして、それに合わないものを劣っていて間違っているという考え方。
大航海時代(と西洋人が主張している簒奪行為)に他の民族を征服するための方便を有り難がって使っているほうが滑稽で間抜け。
文化でも生物でも進化主義って言うのは限定された同一環境の中でこそなんだよ。
だからガラパゴス諸島っていう擬似的な閉鎖環境が研究に向いていたんでしょ。
地域も気候も違う二つの文化を並べて優劣を付けるのはダーウィンもびっくりだよ。
少なくとも鎧甲冑に革靴ってださいよな(´・ω・`)
ほらほら無能韓国人の>>1さん
日本人のふりへたくそですよ
見栄えどうこうってのは今の価値観から来るのであってまったく関係ないよね。
後、>>1が話し通じなさ過ぎてなんだか怖いわ。何のためにスレ立てたんだか。
※44
2chで物事を教えて欲しい時はドヤ顔で間違った事言えば、皆が怒涛の勢いで反論してくるって誰かが言ってたな
草鞋(わらじ)と草履(ぞうり)、どっちかに絞って話を進めて欲しいもの。
草履を履いて合戦はしない。
草鞋ならば合戦のとき、水に濡らせば滑りずらいものと聞いた事がある。手元にあるから今度試してみる。
椅子の文化はなさそうだが、床几ならいくらでもある。
ちなみに草鞋履いて朝鮮国に攻め込んだ秀吉が居た筈。
靴をあの時代に履いてたとして、日本の多湿な気候からして
内側が湿気るせいで不衛生なうえ、素材の調達と加工が面倒=高価になって
どう考えても多くの人々が履けるような代物にはならない。
草鞋や草履などが当時の日本の環境で自然と広まっていったのは極自然だわ。
無知やなあ
釣り宣言がなければ釣りではない
よってただのアホ
2レス目くらいでNG入れてるくらいのウザさ
こういうスレ立てる奴って昔のことを現代の価値観に無理やり結びつけたがるヒステリックな女みたいな頭してるんだろうな
古代日本には鮭皮で作った靴もゲタもあったけど草履がコスパで優秀だっただけ
いまだって沢わたる時草履使うんだが本当に登山したことあんのかこいつ
海外なら中国には出て行ってるし、東南アジアも行ってたんじゃないの?スレ主の言うダサい履物で
それ以上先は造船等の技術の不足とか必要性の少なさで行けなかった、行かなかっただけでさ
うむ。正直にダサい。今の感覚で言うと
だからと言って記録を消したり忘却してもいいわけではない
漫画とか小説で時代劇でみんな草履ではなく革靴を描いていたらかえっておかしいわけね
でもなぜ浸透出来なかった研究をしている姿勢は素晴らしい
これからのファッションを考える時の貴重な資料となるね
さて・・現代のファッションで未来の人に笑わられないように考えなきゃね
なんでこいつこんな必死なの?
幼いころに親に靴を買ってもらえなかった嫌な思い出でもあるんかな?
これは元スレ>>1が文明への理解度が無い教養の無さを露呈してるだけだね
自分の主観と経験が絶対みたいな考えだしいくらバックグラウンドを説いても
受け入れようとしてない
最初から結論出してんじゃないの、自分の中で我儘な意見を変える気が無いまま
そんなわけでこれが締めでいいだろう
「お前がそう思うならそうなんだろ、お前ん中ではな」
そういやなんかの本で「文化というのはその風土・人々の暮らしに合っているかを問わず、
生活上の必要性から仕方なく生まれてくる場合がある。着物を日本人より上手く着こなせる
外国人がいるのは文化の状況を選ばない本質性のためである。」みたいなこと言ってる本思い出した。何が言いたいのかっていうと「合うやつは合うだろうし合わないものは合わない」ってこと。
恥ずかしいとまでは思わん。仮に草履を恥じるもの・低位なものと考えたとして(こういう言い方だとさも現代靴が素晴らしいみたいな言い方と思われるが違う。雪ではブーツよりもカンジキの方が役に立つ場合もある)、その下敷きがあって今の靴の方が昔よりいいみたいな考えになるんでしょ。
その下敷きを恥じるってことは、その経過・移り変わりで培われてきた文化を否定、つまり日本人の国民性や経済的な歴史まで否定するってんだから、元>>1は日本人の気質とは逆行してるよ。
家の中まで靴であがるなんてガサツな文化の方がダッサイわ。
雨の日なんか草履ならすぐ乾くだろうし、何より家に上がるときには脱ぐ。
ところが靴文化ではびちょびちょに濡れたままの靴で家に上がる。
結果として家ん中びちょびちょwww だせえwww
見た目は確かに不格好だが
しかし機能性に関しての知見が浅すぎであろ
いや、ダサイのは確かだろ。恥だとは思わんが。文化だし。
スレ主を納得させるだけの論拠を出せなかった他の奴らの問題。
キムチ臭いなあ
時期的に草履文化を題材に卒論書こうとしてる文系学生でFA
草履なんて使い捨てだよ
濡れたら新しいのを作るだけ
新手の半日か?
悪質な西洋かぶれは死ね
無理矢理にでも馬鹿にしたいみたいだけど、無知だらけでこっちが草不可避だわ
画像も格好悪くないよね。むしろカッコイイんだけど
中二病患者か在日だろうな。
つーか>>1草履と草鞋と地下足袋と区別付いてなくね?
草履は農民の履物だったわけで。
藁あれば作れるし昔は手軽で経済的な履物だったんだろうな草鞋
俺は冬にクロックス履く奴の方が信じられん・・・
材料が入手容易で手軽、土の道を歩く・走るには結構便利だし理にはかなってる。
あと、侍も馬に乗る場合は毛靴を履いたり、徒歩でも草鞋+足の甲側を鉄板・革などで
保護したりと、戦闘に合せて履き物を替えたりオプション着けてたりする。
結構拘ってるのよ。
雑兵なんかは草鞋オンリーが普通だけど、予備の草鞋を1~2足腰に下げたりしておいて
草鞋が濡れたり、すり減ったら履き替えて足回りの快適さをキープしてる。結構合理的よ。